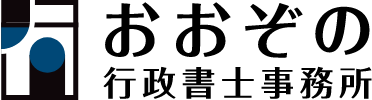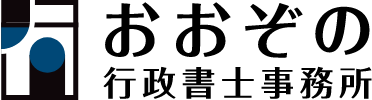- 所長コラム
専任技術者の“通し方”完全ガイド|資格・実務経験・常勤性の立証ポイント
導入
公共工事の入札まで見据えるなら、**専任技術者(常勤)**の証明は避けて通れません。
本記事では、資格ルート/実務経験ルートの通し方、常勤性の立証、よくある差戻しまで、審査で詰まりやすいポイントを実務目線で整理します。読み終えるころには、あなたの会社がどのルートで、どの資料を、どの順番で揃えるべきかが明確になります。
H2: 専任技術者とは何を満たす人か(Know)
役割と位置づけ
許可業種ごとに、営業所ごとに配置が必要な技術責任者。
許可申請・更新・業種追加の根幹資料(経審でも技術職員として評価に直結)。
2つの立証ルート
資格ルート:所定の国家資格・合格証等で立証。
実務経験ルート:所定年数の同種工事経験で立証(業種整合が重要)。
ここでの肝
業種整合(例:電気工事業の経験→電気工事業に対応)
常勤性(勤め先・就業実態・社会保険)
専任性(他社兼務や外注扱いは原則不可)
H2: 資格ルートの通し方(Do)
対象となりやすい資格の例
1級/2級施工管理技士(各種)、建築士、電気工事施工管理技士、管工事施工管理技士、土木施工管理技士 など(業種に適合すること)。
提出書類セット(基本)
資格者証(裏面含む)/合格証明書の写し
本人確認(運転免許等)
履歴書(業務経歴):どの業種に適合する資格かを見出しで明示
常勤性の根拠(後述)
実務Tips
資格名称・区分・旧称の表記統一(書類ごとのブレを消す)。
業種対照表を社内で作り、資格→対応業種のマッピングを一目化。
有効期限・氏名変更の裏付け(氏名変更時は戸籍抄本の写し等で橋渡し)。
H3: ありがちな差戻し例(資格)
資格が対応外の業種に出されている。
合格証のコピー不鮮明(生年月日・登録番号が潰れている)。
氏名表記揺れ(登記・保険・資格で字形が違う)。
H2: 実務経験ルートの通し方(Do)
基本の考え方
所定年数の同種工事経験を、連続性と業種整合をもって証明。
経験の立証パッケージ(例)
工事契約書/注文書・請書、請求書・入金記録、工事写真、完成証明(検査済・引渡書)
在籍・雇用の証明(雇用契約書、賃金台帳、出勤簿、社会保険加入状況)
業務内容の説明書(どの部分が当該業種かを注記。工種名・数量・仕様を引用)
実務Tips
年月の空白期間をなくし、月単位で並べたタイムライン表を作る。
工事種別の整合:土木/建築/専門のどれに該当するか、見出しで明示。
協力会社名義の実績しかない場合の扱いは厳格。自社での従事事実の裏付けが鍵。
H3: ありがちな差戻し例(実務)
工事が別業種(例:管工事に電気工事の経験を混在)。
発注者名・現場所在地が資料間で一致しない。
実務年数のカウント誤り(月割りの端数・休職期間の扱い)。
H2: 常勤性の立証(Know/Do)
必要な視点
勤務の実態:就業場所・勤務日数・勤務時間。
社会保険:健康保険・厚生年金等の加入状況。
給与の支払い実績:賃金台帳・振込明細。
書類例
健康保険標準報酬決定通知の写し、雇用保険適用事業所証明
就業規則抜粋(勤務形態)/出勤簿
給与台帳(直近3か月分を目安)
NGになりやすいケース
他社役員や別会社の常勤と被っている。
個人事業の兼業で常勤性が担保できない。
週数日の非常勤や委託(外注)扱い。
H2: 業種追加・配置転換・拠点変更の注意点(Do)
業種追加
追加先業種に資格/実務経験が合致しているか。
既存業種の専任者配置が空洞化しないか(兼務の可否)。
配置転換
別営業所へ動かす場合は、移動の根拠資料(辞令、勤務表)をセットで。
拠点変更
住所変更・賃貸借契約変更は、営業所実体(机・電話・標識・帳簿)の確認資料も更新。
H2: 提出前セルフチェックリスト(テンプレ)(Do)
表記統一:商号/住所/氏名の字形・ハイフン・全半角
資格 or 実務:どちらのルートかを明確化(混在しない)
業種整合:資格(または経験)→対象業種の論理が資料で一貫
常勤性:社保・給与・就業場所の3点セットで裏づけ
年数計算:月単位で端数を処理(欠勤・休職・産育休の扱いルール化)
不鮮明なし:資格者証・契約書の解像度と読みやすさ
タイムライン:工事実績の連続性が一目で分かる一覧を添付
ダウンロード用に社内テンプレ(タイムライン、業種マッピング表、チェックリスト)を整備しておくと、次回の更新・業種追加が速くなります。
H2: ケース別・実務シナリオ(Know/Do)
H3: 「資格はあるが、氏名が旧姓のまま」
橋渡し資料(戸籍抄本写し等)で同一人を立証。全書類の氏名欄に**(旧姓:○○)**注記。
H3: 「実務経験は十分だが、工事書類が散逸」
発注者・元請に写しの再発行を依頼。最低限、契約書/請求書/写真の3点を回収。
不足分は工事台帳の写しや社内日報で補強(但し自治体の運用に留意)。
H3: 「常勤性で詰まりやすい」
社会保険加入が最優先。加入中でも異動届の反映待ちなどに備え、会社側証明書を併添。
H2: 経営規模等評価(経審)との関係(Know)
技術職員数・資格保有は経審の加点に直結。
許可と同時に、資格取得計画・人員配置計画を年度計画へ落とし込む。
短期:既存人員の証憑整備、中期:資格取得支援、長期:採用と育成。
H2: よくある質問(FAQ)(Know)
Q. 代表者が専任技術者を兼ねても良い?
A. 実態として常勤が担保され、他社兼務等がなければ可能なケースあり。証拠厚めが安全。
Q. 派遣・業務委託の技術者で代替できる?
A. 専任性・常勤性を満たせず原則不可。自社雇用での配置が基本。
Q. 実務経験の“同種性”はどこまで厳密?
A. 許可業種区分に即して判断。工事名だけでなく仕様・数量・工程まで説明すると通りやすい。
H2: まとめ(次アクション)
自社のルート確定(資格/実務)→ 業種整合の見える化 → 常勤性の三点セットを揃える。
明日すぐにやること:
専任候補者の資格・経験棚卸し
タイムライン表と工事証憑フォルダの作成
社保・給与・就業場所の証憑チェック
内部リンク提案(サイト運用向け)
「建設業許可の主要要件チェックリスト(保存版)」
「差戻しを防ぐ提出前レビュー10項目」
「経営事項審査の評点アップ戦略(入門)」
次回は「経営業務の管理責任者(経管)の“通し方”」を実務テンプレ付きで解説します。